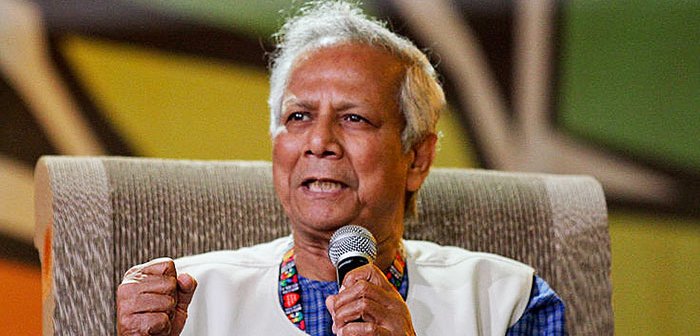『 政府の政策に左右されない暮らし 』
未来バンク事業組合 理事長 田中優
◆日常生活の実験
昔、好きだった大江健三郎の本に「日常生活の冒険」というタイトルがあった。
ちっとも内容は思い出せないが、タイトルが好きだった。考えてみるとぼくは日常生活という言葉に引っ掛かりがあるのかもしれない。背伸びするのは好きじゃないし、大言壮語するより毎日のことを大事にしたい。それで言うならぼくがしているのは「日常生活の実験」だと思う。ご存知の方も多いと思うが、どんなことをしているのか書いてみよう。
◆岡山での暮らし
福島原発事故直後からたくさんの講演会を頼まれ、2011年から2年間は日数よりも講演回数の方が多くなるような暮らしをしていた。毎日遠くへ出かけ、まるで住所不定のような暮らしぶりだった。こんなことができたのも、2008年に仕事を辞めたからだった。以来、原稿書きと講演会、大学の非常勤の仕事などで暮らしていたが、2011年の事故はぼくの暮らしに大きな変化をもたらした。
2012年末、岡山に引っ越した。ぼくが原発に反対であることは、政府の作った「要監視者リスト」に名前が挙がっているくらいだから、周知の事実だったろう。
でも仲良くしている「くりこまくんえん」の大場さんから、「田中さんって原発問題で有名だったんですね、ぼくはただの山好きのおじさんだと思ってました」なんて言われたぐらいだから、あまり自分からは言わないタイプだったのかもしれない。
そして岡山に越してから少しして、再婚した奥さんとの間に子どもが生まれた。こんな安心な場所で子育てできるのは幸いなことだったと思う。



引っ越したのは偶然に近い。「てんつくマン」という友人から、「ビデオ撮りするから来てくれ」と言われ、そのときに「こんなところに住みたいなぁ」と言ったのがこの岡山の和気町だった。今の家の場所を探してくれたのもてんつくマンの奥さんだった。メールで写真を見て、ここにしようと決めてしまった。
ぼくが東京を離れることになれば、「田中優は逃げた」と言われるだろう。
しかし居続ければ「田中優は放射能が危険だと言いながらそのまま住んでいる」と言われる。どちらがいいかと言えば、けなされても危険は避けた方がいい、そう思って転居した。
なぜか引っ越しのときは、今ここで親しくしている岡山の友人たちが徹夜でトラックを運転して荷物を運んでくれた。まだ講演会ラッシュの時期で、引っ越し当日には自分は一緒に来ることができなかった。荷物だけが引っ越した状態だ。当時は古民家を買って住んだのだが、室内にムカデが出たり、動物が入り込んでいて人感センサー付きの照明器具が勝手に点いたりするのが嫌で建て直した。人感センサーならぬ、動物センサーとなっていたのだ。
もちろん家は自分がやっている一般社団法人「天然住宅」の仕様だ。建てるときも自分で決める「分離発注方式」で建てた。大工さんたちは「ベニヤと接着剤を使わずに家が建つのかよ」と言っていたほどだ。それでも満足できる十分な家が2016年に建った。
伝統工法の仕口接手
国産の無垢・防腐剤フリーの杉・ひのきなどで作った
こう書くと東京から離れたように思うかもしれないが、大学の授業は続けているので、授業のある間は毎週東京に来ている。まぁ、会議に追われる東京での滞在時間だが。
◆自立した暮らしを
そして2013年からは電気を自給して電線を切り、文字通りのオフグリット生活にした。その後に庭の井戸跡を見つけて井戸を復活させ、水も自給に切り替えた。
さらに固定電話をやめて携帯と無線のインターネットに変え、固定電話線もカットした。残るはガスだが、太陽温水器を入れて消費量は半分程度に下げた。こうして初期費用はかかるものの、日常生活にかかる費用を極めて少なくした。とりわけ電気の自給はカネがかかるし元は取れないのだが、それでも電力会社との関わりを断ち切りたくてやめた。
電力会社と契約を解除、電線も切ってもらった。完全なオフグリッド
太陽熱温水器
ここまでがこれまでの話だ。そこからも「日常生活の実験」は続く。
あらたに入れたのが無煙炭化器と炊飯器だ。
無煙炭化器
ブラジル・アマゾンの先住民が作り出した「テラプレタ」という奇跡の土がある。なんど作物を収穫しても連作障害を起こさず、土は自分の力で回復していく。そんな土があって、それが人間が作ったものだったとわかったのは2000年を過ぎてからのことだった。その土地は荒れ果てた「ラテライト」で、三作作れば何も採れなくなる。そこに炭と木酢液などを混ぜることで、奇跡の土を作っていたのだ。

しかもそれを作り出すことで、地球の大気に吐き出してしまった二酸化炭素のすべてを、数年のうちに土に吸収させることができるのだ。今回COP22でフランス政府は、耕地の中に0.4%だけ多く炭素を混ぜこむことで、毎年排出する世界の二酸化炭素の75%を吸収できると発表した。これまで厄介者扱いしかされなかった農業者が、最前線となるのだ。炭は木材の持っていた二酸化炭素の8割を閉じ込め、燃やさない限り排出されない炭素の吸収源となるのだ。
この話が面白くて自分でもしたくなった。そこで無煙炭化器を買い込んで、庭で炭作りを始めたのだ。「まぁいつか炭で菜園を作ろう」ぐらいに思っていたのに、急きょ農地が必要になってしまった。それはフェイスブックでGMO(遺伝子組み換え作物)の話を載せたおかげだった。宮崎で農業をしている友人が、「のらぼう菜」の苗を送ってくれたおかげだった。
のらぼう菜は面白い作物だ。ほとんどの野菜の祖先になったアブラナ科の野菜であるにもかかわらず、ちっとも交配しないのだ。普通は勝手に交配して別な野菜を作り出してしまうほどなのに、ちっとも交配しない。交配させて別な種を作ろうとあちこちで試みたのだが、まだ成功できていない。遺伝子組み換え作物によって世界の作物を支配しようとするモンサントのような会社は、自分で作物から種を取ることを禁止しようとするのだが、のらぼう菜は自分で種を取らなければ収穫できず、しかも交配しないのだ。
田中優宅で栽培しているのらぼう菜
これが江戸時代の飢饉の時代に人々を救っている。寒さにも強く、生命力も旺盛で、栄養豊富なのだ。こんな作物が各家庭の庭にあったら、巨大アグリビジネスの支配下にならずにすむではないか。その苗を送ってもらったので、急いで炭を混ぜた自家製テラプレタを庭に作ってみたのだ。今のところのらぼう菜の生命力に救われて、どうやら活着したようだ。
そしてもう一つの炊飯器は、自動でスイッチ一つで「酵素玄米」だろうが「発芽酵素玄米」だろうが炊くことができる優れモノの炊飯器なのだ。玄米はビタミンCを除けば完全栄養だといわれる。調べてみると量的には不足するものの、微量栄養素のすべてを持っている。つまり一汁一菜のように、わずかな副菜があれば、それだけで生存可能なのだ。
炊飯器で炊いた酵素玄米
ときどき言われる玄米のフィチンが微量栄養素を奪ってしまうという懸念は、実際の二年間の実験によって否定されている。これから玄米と一汁一菜で、生命をつなぐことができるのだ。幸い、昔勤めていた会社の親友が、退職して新潟で有機のコメを栽培している。そこから安心できるコメを買えば、ぼくはそれだけで生活できるのだ。
◆自立は孤立を意味しない
こうした暮らしはとても大きな安心感につながる。自立すると孤立するかと思っていたが、自立することでより多くの友人たちが出来てくる。
自立するとおカネのつながりがほとんど消え失せるだけで、孤立の問題はおカネでのつながりのときに起きるようだ。カネでないつながりは、多くの友人を引き付けてくれるようだ。
おかげで心配しなくていい部分が広がった。もちろん家の中には人体に有害な化学物質は使っていないし、食べるものも有害物質はほとんどない。そんな中、ついに60歳の誕生日を迎えてしまった。「ジジイ」という言葉を実感する。
先日検診を受けてみたら、あちこちにガタが来ているのがわかった。
体力だけで乗り切ってきたこれまでの暮らし方を、いよいよメンテナンスしながら暮らしていかなければならない。そこで朝早くからウォーキングすることにした。かつてマラソンをしていたことがあったが、さすがに歳のせいか老練になってくる。タイムなんて考えるよりも、楽しくすることを考えるのだ。
そう思ってウォーキングすると、田舎に住んだことの素晴らしさを実感する。どこを歩いても美しいのだ。今は枯れ木ばかりだが、その木の色が少しずつピンクがかってくる。枝の先につぼみがつくからだ。その後には燃えるように色とりどりの花と緑が吹き出して来るだろう。それを考えると今の風景のピンク色がかった枯れ木も美しく感じるから不思議だ。
ぼくはいろいろ調べてみるのが好きだ。好奇心に任せてあれこれ追いかけるのが。そしてフェイスブックの発信は、いろんな人とつながるばかりか運動の始まりにもなっていく。こんな暮らしをしていて、さらに次の「日常生活の実験」を考えている。
そんな暮らしをするにはとても良い時代だ。友人が新たなエネルギー源のニュースを伝えてくれた。どうなっていくのかワクワクしている。対立して落ち込むこともあるかもしれない。しかしぼくには生活の安心という後ろ盾があるのだ。
もっともっと日常生活の実験を進めていきたい。
以上、2017.3発行
※「未来バンク事業組合ニュースレター No.90/2017年3月」より抜粋
PDF版はこちら
http://www.geocities.jp/mirai_bank/news_letter/MB_NL_90
○●○ 無料メルマガ 「未来バンク事業組合ニュースレター」 ○●○
田中優が理事長を務めます未来バンク事業組合の無料メルマガです。
金融のスペシャリストでもある未来バンクの他メンバーたちによるコラムも必見です。
バックナンバーは「非公開」ですので、ご興味のある方はこの機会にぜひご登録ください
ご登録はこちらより http://archives.mag2.com/0001300332/
【最新号メルマガ 他の主な内容】
■「遺伝子ドライブと化学物質の噴霧による作物の増収」木村瑞穂
■「同胞ということ~津久井やまゆり園の事件を受けて~」 岡田 純
■「トランプ大統領はどう進むか・・・?」奈良由貴