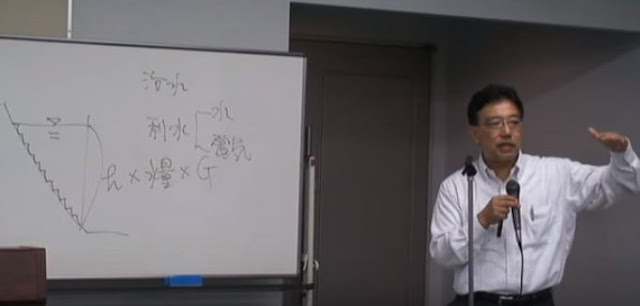2019.12発行 メルマガより
多くなる災害廃棄物
今年の台風の被害は大きかった。
連日テレビに映る被災地では、水害後の道路にはうず高く廃棄物が置かれ、ほとんど丸々一軒の家屋が廃棄物となっている。
畳を上げ、床を剥がし、床下や壁の内側に使われたベニヤ板を捨て、停電で腐った冷蔵庫の食品も、もちろん水を浴びた電化製品や家具類もまた廃棄されている。
前から災害のたびに、これほど大量の廃棄物が出されていたのだろうか。
もちろん水害のせいもある。水害では自分の命を守るのにやっとで、家財など命に比べたら物の数ではないだろう。それにしても家一軒丸ごと廃棄物にすることはなかったのではないか。しかも水害の保険は加入していたにしても床上浸水でなければ保険金が下りず、床下までは保険の対象にならない。
どうやらこれは家の造りに原因があるようだ。今の家は集成材で作られ、ベニヤ板で補強され、家具もMDF(中密度繊維板)と呼ばれるは、木材チップを原料としてこれを蒸煮・解繊したもの に合成樹脂を加えて成形したものだ。
これらのものは水に触れると膨れ上がって歪み、元の形に戻らなくなる。しかも樹脂が固める際には防腐剤を大量に加えているはずなのに、腐ってカビだらけになって、気味の悪いとりどりの色になる。
昨年ぼくの住む岡山にも水害があり、手伝いに行った人々が嘆いていた。無垢材で建てた家は洗って干せば使えたし、歪んでいるなら削って直せたのだが、今の家はどうにもならないと。
そう、かつては再生できたのに、最近建てられた家ほど捨てるしかないのだ。
これは建物の話だが、修復が効かないものが社会全体を覆ってしまっているようだ。
何が洪水を防いだか
東京の東側にある利根川水系では水害が少なく、西側の世田谷区・大田区、神奈川県川崎市では水害が大きかった。調べてみると水害の防止に大きく役立ったのが、利根川水系にある「
遊水地」だった。鉱毒事件を発端として作られた渡良瀬川添いの遊水地や、周辺の遊水地が溢れる水を一時的に貯留し、水位が下がると川に戻して水害を防いでいたようだ。
政府は偶然「試験湛水中」だった八ッ場ダムのおかげで洪水が防げたかのような宣伝をしているが、もしそうならダム建設後に予定している水位では、洪水防止効果はほとんどなくなってしまう。
しかし今回の豪雨でも八ッ場ダムの貯水効果は、利根川中流域でもわずか17センチほどしかなかった。
もともと河川水位から見て、水害を心配するレベルには達していなかったのだ。
ダムが川の水位を下げる効果は下流に行くほど小さくなるので、八ッ場ダムは東京の洪水防止には影響しなかったのだ。
多摩川水系には遊水地を造れるほどの余地がなく、しかも堤防が決壊しないように造られてなかったことが被害を大きくした。しかし「堤防」を決壊しないように造ることはできるのだ。
旧建設省が二年間だけ採用していた「フロンティア堤防」というものがある。
河川が越流し、堤防を溶かして大水害にしまうことで被害が拡大するのを防ぐのに、堤防の天端に鋼矢板を刺して補強し、堤防の弱点となる住宅地側のり面(裏のりという)を安価なシートなどで保護して補強すればよかったのだ。ところがそれは「(簡単に対策できるので)ダム建設の妨げになる」という理由の反対があり、そしてお蔵入りしてしまった。
今回の水害で、長崎県で建設を推進している石木ダムの担当課長が、「相次ぐ大型災害はダム建設にとって追い風」という発言をして問題になった。後に撤回したが、この発言のように、水害はダムを造るための理由として利用されている。ダムよりもっと安くて簡単な方法があるのに、彼らの利権を守るために無視される。
もし川の水位上昇が心配なら、河床を掘削して水位を下げられるようにすればいい。放置して河床を上げるから、水害時の越水を心配しなければならなくなるのだ。
ダム推進のためにすべきことを怠り、対策をなおざりにする。
「事前放流」せずに「緊急放流」する
もう一つ気になるのが
ダムの運用だ。ダムは事前に放流して水位を下げておけばそれだけ貯められる量が増える。しかしダムは完璧な対策ではないから、ダムが大きくなるとそれだけ万が一の水害を大きくする。「安全保障のための軍事拡大」のようなイタチごっこを招くのだ。安全性を考えてダムを大きくすると、万が一の際の被害を大きくする。
それに加えて危険にしているのが「多目的ダム」だ。洪水防止が唯一の目的ならダムを空にしておくのがいい。ところが発電目的や工業・農業用水目的が加わると、貯まった水は「おカネ」と同じになってしまうのだ。
事前にダムの余力を作るための「事前放流」も、それらの関係機関と協議してからでないと「事前放流」ができない。いよいよこのままではダムが破壊されるという時点になって、「緊急放流」して貴重な人命や財産を危険にさらすのだ。緊急放流の怖さは昨年の愛媛県・肱川や岡山の高梁川で嫌というほど目にしたというのに。
そんな中で突然に「記録的な短時間大雨情報」が出されるようになった。降水量は海水の温度に比例して大きくなり、しかも日本近海の海水温は上がり続けている。
地震の多い日本に原発が無理であるのと同じように、今後さらに短時間の降水が予想される日本の水害に、ダムで対策するのは無理になる。
「ダムで水を受け止める」という発想ではなく、「しなやかに流れを受け止められる」方向に進むべきだ。そのことは国や自治体だけではない。私たちがどこに住むかを考えるときにも、どのような家を建てるかを考えるときにも必要な発想になる。
今回、国も自治体も「想定外」という言葉を連発した。想定外の豪雨だとか想定外の台風とか。ならば想定すればいい。地球温暖化が進展している以上、その言い訳は通用しない。
私たち自身が問題を理解しないと危険な時代になった。
他人任せにはできないのだ。
 |
| イメージ |